今回も中小企業診断士の勉強方法について、ご紹介していこうと思います。
先日、1次試験の勉強方法を紹介したので、今回は2次試験の勉強方法をについて説明していきます。
中小企業診断士の資格は、1次試験で7科目もあり、難しいのですが、2次試験はその1次試験の合格者のうち約2割程度しか合格できないことから、2次試験の難易度は非常に高いです。
加えて、中小企業診断士の2次試験の難しい点は、記述の解答が予備校によって微妙に異なることにあります。
つまり、課題をもった中小企業が題材となり、その課題を解決することがメインとなる問題が多いのですが、予備校によって微妙に問題の捉え方や解答の方針が異なるのです。
私は、不動産鑑定士の試験に合格しておりますが、不動産鑑定士の論文式試験の場合、不動産鑑定評価基準という絶対的なものがあるため、それを軸に解答を構成すれば、ほぼ間違いないですし、予備校間におけるばらつきが少ないという印象です。
よって、このように難関な中小企業診断士の2次試験を突破するためには、勉強方法を確立することが必要不可決となるのです。
◇まず2次試験の特徴を知ろう!
中小企業診断士の2次試験は、事例問題が出題されます。
事例問題は計4つあり、各事例問題の解答時間は80分間です。
また、事例ごとにも特徴があり、対策を講じる必要があります。
事例Ⅰ 組織論
事例Ⅱ マーケティング
事例Ⅲ 運営管理
事例Ⅳ 財務・会計
これらの事例がある中で、合格するために必要な対応とは?
結論から言うと「事例Ⅳの財務・会計を極めて、事例Ⅰ~Ⅲは他の受験生と同等の解答を作成できるようにする」です。
なぜ、事例Ⅳを極める必要があるのか?
理由は、財務・会計は計算問題であるため、受験生間での得点差が如実に出やすいからです。
さらに、計算問題を完璧にこなせば、8割の得点も可能です。
4科目で6割の得点で合格できるであろうと言われている2次試験において、事例Ⅳで8割程度得点できることのメリットは相当大きいです。
だからと言って、他の事例が手薄になっていいという訳ではありません。
他の受験生と同等の解答作成能力が求められます。
では、その同等の解答作成能力をどのようにして養えばよいのか気になりますよね?
次回、具体的な勉強方法について言及していきます。(続き(勉強方法その2)はこちら)
私のブログが皆さんのお役に立つことができることを祈っております。
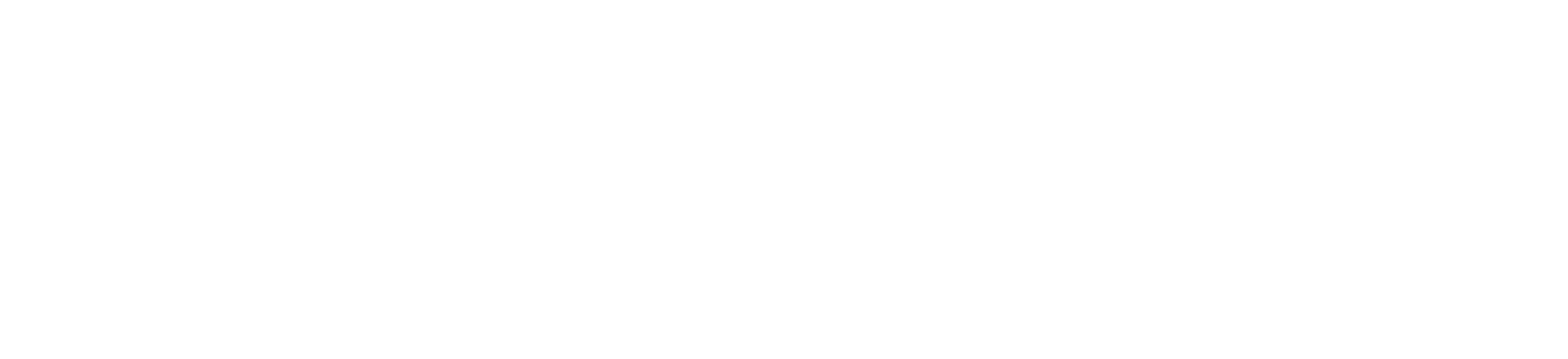











コメントを残す