働きながら不動産鑑定士と中小企業診断士になったズーヤンです。
働きながら不動産鑑定士の論文式試験まで合格したことがある人はかなり少ないと思うので、この記事はあなたのお役に立てると思います。
この記事は次の人向けに書いています。
・「仕事で忙しくてなかなか時間が取れない。でも不動産鑑定士になりたい」と思っている人
この記事を読むことで、あなたは仕事しながら不動産鑑定士に合格するための勉強時間が分かります。
それでは、結論から言いますね。
「え!?平日に6時間も勉強できるの?」
安心してください。
スキマ時間をかき集めればできます!
詳細について説明していきますね。
1.不動産鑑定士試験の概要

まずは、不動産鑑定士試験の概要について説明します。
不動産鑑定士試験は大きく2つの試験に分かれています。
第一関門:短答式試験
第二関門:論文式試験
短答式試験は、マーク式試験のことで、①鑑定理論、②行政法規の2科目で構成されています。
論文式試験は、記述式の試験のことで、①鑑定理論×2、②鑑定理論(演習)、③民法、④会計学、⑤経済学の計6科目で構成されています。
短答式試験の合格率は30%程度、論文式試験の合格率は15%程度です。
短答式試験に合格すれば、合格した年を含めて3年間論文式試験を受験することができます。
もし、3年以内に論文式試験に合格することができなければ、もう一度短答式試験を受験し直さなければなりません。
2.一般的に不動産鑑定士試験に合格するための勉強時間とは?

そもそも一般的に不動産鑑定士試験に合格するための勉強時間って知っていますか?
いろんな資格の勉強時間をまとめているようなサイトやブログがあると思うので、検索したらすぐに出てきます。
私が検索してみた感じだと、ざっと2000〜2500時間ってところでしょうか。
実際にこんなに必要なの?と疑問に思うかもしれませんが、だいたい当たっているような気がします。
ただし、何度も受験しているような人はさらに勉強時間は増えるでしょう。
ちなみに、私の場合も勉強時間は短答式と論文式試験の合計で2500時間くらいだと思います。
不動産鑑定士試験の場合、短答式試験と論文式試験があるので、それぞれ勉強時間の配分は違います。
もちろん論文式試験の方が勉強時間が長いです。
私の場合だと次のようなイメージです。
- 短答式試験→300〜400時間
- 論文式試験→2100〜2200時間
3.短答式試験の勉強時間

さきほど短答式試験の勉強時間は300〜400時間と書きましたが、「平日と休日でどのくらい勉強したの?」と思いましたよね。
私の場合、平日で2〜4時間、休日で6〜8時間くらいでした。
働きながら受験したので、仕事から帰宅した夜に勉強していました。
もし、あなたが宅建(宅地建物取引士)を持っていたり、マーク式試験が得意であれば、もっと少ない時間で合格することができます。
合格率も30%なので、比較的合格はしやすいです。
4.論文式試験の勉強時間

無事短答式試験に合格しても、安心しないでください。
本番はここからです。
短答式試験と論文式試験では難易度に天と地ほどの差があります。
ドラクエⅦでいうと、短答式はオルゴデミーラ(変身前)、論文式試験はオルゴデミーラ(最終形態)くらいの難易度の差があります。
要は、論文式試験の方が短答式試験よりも圧倒的に難しいということです。
私の場合、試験直前の5ヶ月間は、平日で6時間、休日で10〜12時間くらい勉強しました。
1度論文式試験に落ちたということもあり、2度目は絶対に合格するぞ!という気持ちで頑張りました。
5.スキマ時間をかき集めまくる!

でもさすがに、平日6時間も勉強するのは無理!!と思ったあなた!
意外と平日6時間って勉強できますよ。
私が徹底していたのはスキマ時間をかき集めまくるということです。
私の場合、平日の勉強時間6時間の内訳は次のような感じです。
昼休み→0.5時間
仕事の移動時間、電車の待ち時間→0.5時間
帰宅後→4時間
頑張れば、平日6時間の勉強時間を確保できると思いませんか?
ちなみに休日は、起きている間ずっと勉強していたので、勉強時間10〜12時間です。
6.まとめ
いかがでしょうか?
これまでの記事の内容をまとめると次のとおりです。
・短答式試験→300〜400時間(平日で2〜4時間、休日で6〜8時間)
・論文式試験→2100〜2200時間(平日で6時間、休日で10〜12時間)
・勉強時間を確保するためにスキマ時間をかき集めまくるべし!
これであなたも不動産鑑定士合格への道のりのイメージがわいたのではないでしょうか。
この記事が、不動産鑑定士を目指すあなたのお役に立てば幸いです。
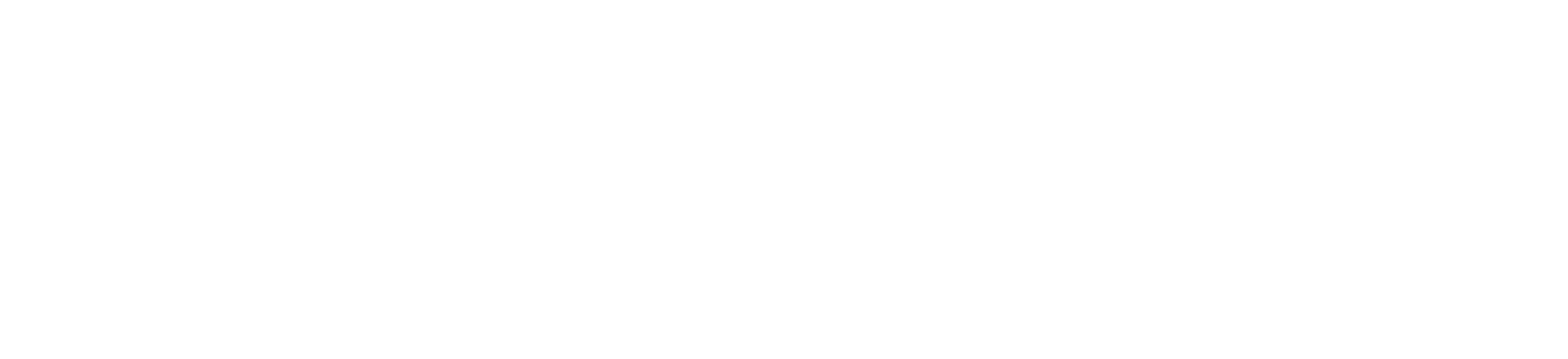














コメントを残す