こんにちは。
前回までは、働きながら不動産鑑定士試験に合格した方法を説明してきました。
見逃した方はこちらを参照願います。
今回は、働きながら中小企業診断士の試験に合格する方法(ノウハウ)をご紹介していきたいと思います。
ノウハウは大まかに分けて3点あります。
①心構え
②具体的な勉強方法
③スケジュール管理
この3点を徹底すれば、合格にかなり近づくことができると思います。
(最終的に合格できるかは本人次第であることは言うまでもありませんが)
それでは具体的に説明していきます。
①心構えについて
当然のことではありますが、本当に合格したいと渇望することが重要となります。
なれたらいいなという気持ちではなく、絶対に合格したい。合格できなかったら、自分は一生ダメなんだというくらい背水の陣で勉強することが重要になります。
ちなみに私は、これで合格できなかったら、自分は社会人として一生自信が持てずに過ごすことになるという気持ちで勉強しました。
皆さんの心構えの参考になったら幸いです。
厳しいかもしれませんが、中途半端な気持ちでやるなら、時間の無駄なので、そもそもやらない方がよいかもしれません。
②具体的な勉強方法について
中小企業診断士の試験は、1次試験と2次試験の2段階あります。
まず、1次試験の場合、テキストと問題集については、TAC出版のスピードテキスト、過去問題集をオススメします。
理由は、受験生人気No.1というだけあって、解説が分かりやすいというところにあります。
ちなみに、私は1次試験は独学で勉強していたので、講義はYouTubeにアップロードされているTBC受験研究会の講義動画を見ていました。
次に、勉強のやり方が難しいと言われている2次試験の勉強方法を紹介します。
中小企業診断士の2次試験は、事例Ⅰ~Ⅳの4事例各80分の試験で行われます。
事例Ⅰは組織論、事例Ⅱはマーケティング、事例Ⅲは運営管理、事例Ⅳは財務・会計という内容となっております。
2次試験のカギとなるのは、ズバリ事例Ⅳです。
事例Ⅳは計算問題なので、できる人とできない人の差が明確に出ます。
受験生の中には公認会計士などの会計に精通した受験生もいるので、ほぼ間違いなく高得点をとってきます。
一方、事例Ⅰ~Ⅲは、何かしら課題を抱える中小企業の課題を解決する提案などを論述する形式となっているので、どうしても差がつきにくいです。
よって、事例Ⅳの過去問は、毎日解くようにした方がよいです。
ただ、事例Ⅰ~Ⅲが手薄になっていいという訳ではありません。
当然のことながら5~6割程度とれるくらいの実力をつけるように勉強する必要があります。
そこで、事例Ⅰ~Ⅲの勉強方法が気になるところかと思いますが、80分まるまる使って事例問題を解く練習をするのではなく、30分で回答のキーセンテンスをピックアップする練習をすることをオススメします。
なぜなら、大幅に時間短縮して過去問の回転をあげることができるからです。
中小企業診断士の受験生の多くは、多忙な会社員が多いと思います。
よって、効率を追求するとキーセンテンスのピックアップ練習をして、あとはそのキーセンテンスをつなげるだけの状態にすることで、効率的に学習を進めることができるんです。
もっと具体的な説明については、別の記事で説明させていただきたいと思います。
③スケジュール管理について
最後に、意外と難しいスケジュール管理について説明していきます。
中小企業診断士の試験では、受験に専念している人はかなり少ないと思いますので、スケジュール管理が非常に重要になってきます。
スケジュール管理といったら難しそうに聞こえますが、要はいかに勉強時間を確保するかということです。
私の場合、朝1時間、通勤時間、帰宅(21時くらい)後2~3時間を勉強時間に充てていました。
朝のテレビ、夜のお酒などの誘惑を一切絶ち、勉強に費やしました。
特別なテクニックはいらないです。
寸暇を惜しんで勉強をすることができるかに尽きます。
半ば精神論的な感じですが、意識が変われば、自然と行動が変わってきます。
働きながら受験するためのノウハウは以上です。
皆さんのご健闘を祈っております。
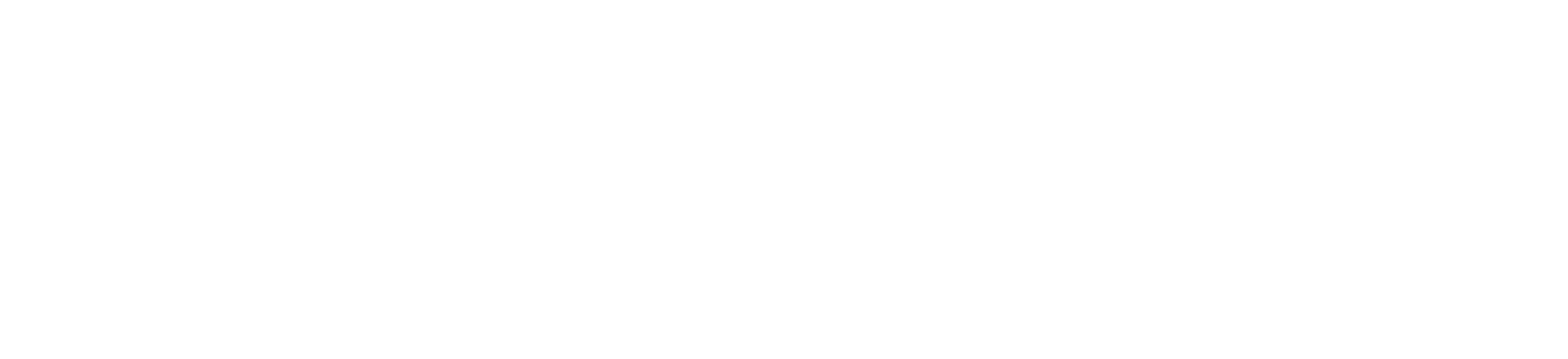










コメントを残す