不動産鑑定士、中小企業診断士のズーヤンです。
不動産鑑定士試験においては、暗記が重要か?理解が重要か?議論されることがよくあります。
そこで、この記事は次の人向けに書いています。
・「鑑定理論は膨大な暗記量だから、暗記の方が重要だ!」と考えている人
・「論文の構成をするために理解は必須!理解の方が大事だ!」と考えている人
この記事を読めば、暗記と理解のどちらが大事なのか、なぜ大事なのか、明確になります。
早速ですが、結論を言いましょう。
結局両方大事なんかいっ!と思いましたよね?
両方大事です。
なぜ暗記と理解が両方大事なのか?詳しく説明していきますね。
1.不動産鑑定士試験の概要

まずは、大前提として不動産鑑定士試験の概要について説明します。
不動産鑑定士試験は大きく2つの試験に分かれています。
第一関門:短答式試験
第二関門:論文式試験
短答式試験は、マーク式試験のことで、①鑑定理論、②行政法規の2科目で構成されています。
論文式試験は、記述式の試験のことで、①鑑定理論×2、②鑑定理論(演習)、③民法、④会計学、⑤経済学の計6科目で構成されています。
短答式試験の合格率は30%程度、論文式試験の合格率は15%程度です。
短答式試験に合格すれば、合格した年を含めて3年間論文式試験を受験することができます。
もし、3年以内に論文式試験に合格することができなければ、もう一度短答式試験を受験し直さなければなりません。
2.不動産鑑定士試験に暗記は必要なの?

そもそも不動産鑑定士試験に暗記が必要なのか気になりますよね。
不動産鑑定士試験で暗記は超重要です。
ただし、短答式試験においては、暗記はそこまで必要ありません。
一方、論文式試験は、暗記が超重要です。
論文式試験→暗記が超重要
理由は試験の解答の特性にあります。
短答式試験においては、マーク式なので、5択のうち1つを選べば正解することができます。
しかし、論文式試験は、鑑定評価基準を暗記した上で解答を作成する必要があります。
これは鑑定理論に限られず、会計学では会計基準、民法では論証例の暗記をした上で、解答を作成します。
なぜ、解答を作成するのとき、暗記した文章を書くのか?
それは、暗記した文章には、採点者が×(バツ)をつけることができないからです。
つまり、鑑定理論の科目の場合、論文の構成が間違っていなければ、鑑定評価基準をうまく活用した論文に対して、採点で×(バツ)をつけることができません。
したがって、不動産鑑定士試験では、暗記が超重要と言われています。
3.不動産鑑定士試験で理解は重要なの?

不動産鑑定士試験では、暗記が超重要と言われる一方で、理解の方が重要だ!という意見を聞くことがあります。
この意見が意味するところは、暗記をしただけでは、鑑定理論や会計基準、民法、経済学を本質的に理解することができず、もし初めて見るような問題を見た時に、対応ができないということです。
不動産鑑定士試験では理解が超重要であるという意見は正解です。
論文式試験→超重要
なぜなら、最近の論文式試験を見ていると、単純な暗記をした文章をペタペタと貼り付けるだけでは、得点することができない問題が増えてきています。
また、短答式試験の場合は、暗記がそこまで必要ない分、理解をしていないと解けません。(もちろん最低限の暗記は必要ですが。)
4.結局、理解と暗記の両方が大事!!

これまで、理解と暗記の重要性について説明してきましたが、結論としては、暗記と理解は両方とも大事です。
言い方を変えると、理解と暗記を交互に繰り返すことで、理解と暗記が深まっていきます。
それなら、理解と暗記はどっちが先なの?という疑問が出てきますよね。
私の意見は、「ざっくりとした理解」が先です。
ざっくり理解→暗記→理解→暗記→理解→暗記→理解
理解と暗記のサイクルを高速で繰り返すことで、理解と暗記が深まっていきます。
5.まとめ
いかがでしょうか。
不動産鑑定士試験で理解と暗記のどっちが大事なの?という疑問に対する答えとしては、
理解と暗記の優先順位は「ざっくりした理解」が先
次のように、理解と暗記のサイクルを高速で繰り返すことで、理解と暗記が深まっていきます。
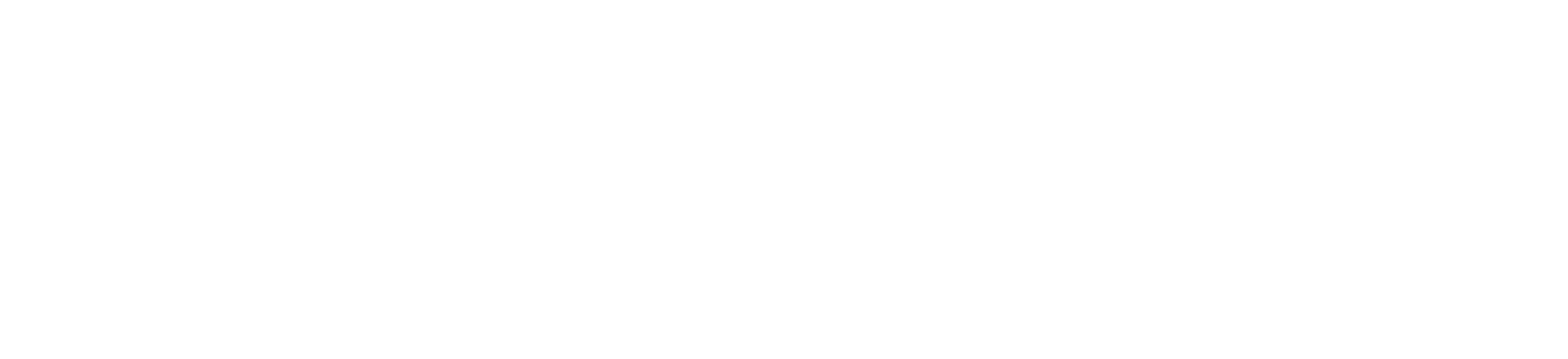
















コメントを残す